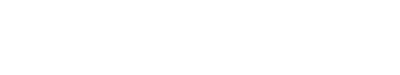角川映画と薬師丸ひろ子と『バラエティ』【新保信長】新連載「体験的雑誌クロニクル」12冊目
新保信長「体験的雑誌クロニクル」12冊目
春樹の期待どおり、薬師丸ひろ子は角川映画のドル箱女優として83年『探偵物語』(原作:赤川次郎、監督:根岸吉太郎)、『里見八犬伝』(原作:鎌田敏夫、監督:深作欣二)、84年『メイン・テーマ』(原作:片岡義男、監督:森田芳光)、『Wの悲劇』(原作:夏木静子、監督:澤井信一郎)と立て続けに主演。新進女優役を演じた『Wの悲劇』では第9回日本アカデミー賞優秀主演女優賞、第27回ブルーリボン賞主演女優賞など多くの賞を受賞した。
その薬師丸に、82年の「角川・東映大型女優一般募集」オーディションでグランプリを獲得した渡辺典子、特別賞の原田知世を加えた“角川三人娘”が、『バラエティ』の表紙やグラビアを飾る。渡辺典子、原田知世も他のメディアにはあまり出なかったので、この3人のファンにとって同誌は聖典のようなものだった。特に長女格の薬師丸ひろ子は出ずっぱりで、『バラエティ』=薬師丸ひろ子と言っても過言ではない(いや、『バラエティ』=原田知世だ、という派閥もあるとは思うけど)。
しかし、『バラエティ』は単なるアイドル雑誌ではなかった。1977年10月創刊号の表紙には「新しいイベント・マガジン誕生!」とのキャッチコピーがある。誌面には公開間近の自社作品『人間の証明』の情報、同じく公開直前の『世界が燃えつきる日』、翌年公開の『スター・ウォーズ』といった海外SF大作の解説のほか、ロードショーや名画座、各種コンサート、演劇、美術展などのスケジュール、FMラジオの注目音楽番組ガイドまで掲載しており、当時全盛のイベント情報誌としてのスタートだったのだ。
それは、五木寛之との巻頭対談における角川春樹の言葉にも表れている。
〈(『バラエティ』は)映画が中心ですけども、映画雑誌ではなく、文芸雑誌でもない。ニュー・マガジンとしか言いようがないんですけどね。「ぴあ」とか「プレイガイド・ジャーナル」とか、情報誌の要素も盛りこんでしまう。情報の震源地が自らつくる映画+αの情報誌、鮮度も感度も十分です〉
自社の映画の情報発信、つまり宣伝がメインと自分で言ってしまってるのがすごい。というか、社長自らが新雑誌の巻頭で作家と対談するというのも、さすが春樹というしかない。宣伝を主目的とした媒体であるからして、ボリュームの割に価格は安く190円だった(その後、250円、330円、390円と徐々に値上がり)。

実際、角川映画の記事に多くの誌面が割かれていたが、それは読者にとって必ずしも悪い話ではなかった。角川映画は、旧来の暗くて重苦しい日本映画の世界に、新風を吹き込んだ。今と違って興行収入上位を洋画が占めていた時代に、メディアミックスでヒット作を連発。前出の薬師丸ひろ子主演作のほか、『蒲田行進曲』(原作:つかこうへい、監督:深作欣二)、『時をかける少女』(原作:筒井康隆、監督:大林宣彦)、『麻雀放浪記』(原作:阿佐田哲也、監督:和田誠)など、映画史に残る名作も生まれた。そうした映画の情報をいち早く、たっぷり得られるのが『バラエティ』だったのだ。
もちろん角川以外の映画や音楽関連の記事も多かったし、インタビューや対談も豪華である。松田優作、水谷豊、細野晴臣、沢田研二、萩原健一、竹内まりや、松任谷由実、鈴木慶一、矢野顕子、桑田佳祐、荻野目慶子、真田広之、松坂慶子……と、名前を挙げればキリがない。
もっとも、こうした芸能関係の人気者が雑誌に登場するのは、ある意味、当たり前だ。それはそれでうれしいが、ほかの雑誌でも見ることはできる。私が『バラエティ』を買っていた大きな理由は(薬師丸ひろ子を別にすれば)、むしろ連載のほうにあった。